中国は、これまで一度たりとも「民心を得た者が天下を取る」ということがなされたことのない、悲しむべき国である。現在、中国の民間には、十分に中共に対抗できるような勢力はなく、また諸外国も、経済利益が絡んでいるため、中共に実質的な制裁を加えることはあり得ない。中共が、すでに何年も前から民心を失っているにもかかわらず瓦解していない理由はそこにある。
7月1日の中共結党記念日がやってくると、国内外では中共に関する議論がにわかに盛んになる。人々がいちばん激しく攻撃しているのは中共の度を超した腐敗ぶりであり、人々がいちばん憤慨しているのは中共のはなはだしい独裁ぶりであり、そして人々がいちばん関心を寄せているのは、中共がいつひっくり返るのかということである。
反腐敗と腐敗の中で、もがきながら前進
中共は1921年に創立され、66年にわたって中国を統治してきた。毛沢東が権力を握っていたとき、中共はずっと国と民に災いをもたらすばかりだった。鄧小平による改革開放は経済を発展させたが、役人のことごとくが汚職に手を染めるほど汚職腐敗が横行し、中共は恥も外聞もかなぐり捨てた「汚職腐敗党」に成り果てた。
習近平は、「劇薬を使ってでも痛いを取り去り厳罰を科してでも無秩序を正すという決心と、骨を削ってでも害毒を取り除き腕を断ってでも生きるのだという勇気を持ち、断固として党風簾政な政治建設と反腐敗闘争を徹底的におこなわなければならない」という誓いの言葉を述べている。そして、これまで109頭の「虎」(副省級以上の党・政府・軍の役人)を退治している。
多くの人は、「中共がこういうふうに反腐敗闘争を続けていけば、シンガポール(やはり一党による長期政権がおこなわれている)の人民党のように、廉潔で公のために尽くす政党になるに違いない、中国には希望ができた」などと考えて喜んでいる。
しかし、そう考えるのはとんでもない間違いである。
中共はこれまで何度も汚職役人を厳罰に処してきたが、奏効したためしはない。たとえば毛沢東は1952年、天津地区党委員会書記の劉青山と張子善を、「国家の資材を盗むという厳重な汚職の罪」を犯したとして、相次いで銃殺した。
また鄧小平は1983年、6万元あまりの賄賂を受け取った広東省海豊県党委員会書記の王仲を銃殺した。そして江沢民は2000年、情婦の李平とぐるになって4000万元相当の金品を賄賂として受け取った人民代表大会副委員長の成克傑を死刑に処した。
そしてまた胡錦溝も2007年、妻と共に650万元の賄賂を受け取った国家食品薬品監督管理局局長・鄭筱英を死刑にしている。中共の反腐敗闘争はなまぬるいものとは言えないのに、汚職腐敗はますます猖獗を極めているのである。
もっと失望させられるのは、習近平は腐敗を予防するような改革的な措置を何ら講じていないことである。習近平は、人を逮捕することに関しては恐ろしい形相で事に当たっているが、政治体制は微動だにしていない。
たとえば各級の役人の任用は、依然として、権力の世襲・縁故採用・官職売買という封建的なパターンであり、民主的な選挙はなく、まして法治の監督はおこなわれない。
歴史学者であったイギリスのアクトン卿は、「権力は腐敗する、絶対的権力は絶対的に腐敗する」と言ったことがある。中共は、監督・牽制・弾劾・罷免を受けないという絶対的権力を死守しているが、それは、如何なる法律も超越した特権であり、衆人の耳目を塞ぎ真実を覆い隠すことのできる権力にほかならない。
人民代表大会や政治協商会議には中共を監督する気持ちがなく、民主党派には中共を監督する能力がなく、マスコミには中共を監督する方法がなく、人民大衆には中共を監督する勇気がない。これでは、どうして中共の腐敗を根本的に除去することなどできようか?
もちろん、習近平は「虎を叩く」棍棒を放り出すようなことはしないはずである。選択的な反腐敗闘争が権貴集団の利益に抵触し、また曾慶紅が中南海を大いに騒がし、そしてこの4月以来「虎退治」の頻度は明らかに下降してはいるが、習近平は「古くからの同志」や革命第2世代の支持を受け、中共で3人目の強力な領袖となっている。
かたくなに独裁を続ける中共
中共の極悪非道な一党独裁は、つとに天からも人からも恨みを買っている。2013年、新疆では8月に雪が舞うという珍しい現象が見られた。また今年の4月中旬、北京では2002年以来もっとも激しく砂塵が吹き荒れた。新疆のウイグル人の武力による反抗を皮切りに、各地の民衆による権益保護事件が次から次へと発生し、1国2制度の香港でも歴史始まって以来のもっとも深刻な「中環占拠」運動が勃発するという具合に、中共は、戦火が四方で起こる苦境に直面している。
中には、こういう現象から判断して、世界は発展しつつあり、社会は進歩しつつあり、人民は覚醒しつつあり、民主の潮流の勢いは止めることができず、中共は必ずこの潮流と時代の趨勢に順応し、民主に向かって進むはずである、などと言う人もいる。
しかし、それはきわめて単純で幼稚な一方的な願望というものだ。
中共にも、かつては、民主に向かって進むという考え方があったことは否定できない。だが、中共の言う「民主」とは、中共による一党独裁および中共の利益が損なわれないことが確保された状況の下で、民衆に少しばかりの権利をくれてやる、というものなのだ。
だから、ひとたび形勢が不利になり、中共の利益が犯され、その地位に危害が及べば、ただちに手のひらを返したようにして、民衆に少しばかりの権利を与えることも拒絶してしまう。
鄧小平と江沢民が、当初考えていた改革路線から反改革路線へと方向転換したのが、そのいちばん良い例である。
1980年8月、鄧小平は政治局拡大会議で「党と国家制度の改革」という講話をおこない、党政分離の構想を提出した。しかし、ポーランドの独立自主管理労働組合「連帯」が全国規模の一大ストライキを発動し、政府に戦いを挑んだことを受けて、鄧小平は、改革をおこなえば党の指導が弱くなり、自身による統治が脅かされるのではないかと恐れ、その党政分離構想を実施に移さなかった。
だが1986年、鄧小平は再び政治改革の話を持ち出した。そして五人小組によって、「党と政府の分離・民主的な協議・大衆による監督」を実施するとした「政治体制改革に関する総体的構想」が打ち出され、それが第12期7中全会で採択された。
ところが、1989年、官僚ブローカーに反対し腐敗に反対することを叫びついには6月4日の第二次天安門事件につながってしまう民主化運動が発生した。これに逆上した郵小平は、一切の改革を叫ぶ声を押さえつけてしまったのだった。
また、第二次天安門事件で流れた血の跡を踏みつけて政権の座に就いた江沢民は、1997年、改革をおこなうことによって自分の悪名を名声に転じようと考え、その調査研究報告書を温家宝に作らせた。
そして、中共第15回全国代表大会から同16回全国代表大会の間に、政治改革構想のための中央委員会全体会議を召集しようと準備していた。その後、「法輪功」学習者が大挙して中南海を包囲するという事件が発生すると、江沢民は前後の見境もなく怒りながら「国の統治と安定を図るためには、党の指導を堅持し強化するしかない」と言い、改革方案を粉砕したのだった。
覇権主義の中共が、自分から進んで自分を根本的に改革したいなどと思うだろうか?そんなことは絶対にあり得ない!1999年以降、江沢民も胡錦溝も政治改革の問題を口に出そうとはしなかった。
習近平は、第18期3中全会で、「改革を全面的に深化させる」などと言う決定を採択したが、毛沢東という悪しき皇帝による共産主義的統治路線を踏襲する習近平は、江沢民や胡錦溝よりもいっそう厳格な独裁統治をおこなっている。
窮地に立ちながらも揺るがない中共
中共が政権を握って60余年、その中共に対しては、国内で民衆による不満の声が渦巻いているだけでなく、国外でも、尊大横暴をきわめている中共は四面楚歌の状況に陥っている。中共がまもなく瓦解するだろうということは、人々の熱い議論の話題になっており、海外のメディアにも「間近に迫った中共の崩壊」といった種類の論評が現われている。
だが、それは1種の軽率な判断であり、実際の情況とは符合していない。
1つには、国内には十分に中共に対抗できるような勢力がないことが挙げられる。中共はすでに強大な統治集団になっていて、特に習近平は、革命世代の子孫ではない役人を処分し続け、各方面の権力をそういう革命世代の子孫に握らせるようにして(たとえば軍の将帥は、基本的にはみな革命世代の子孫である)、政権を全面的に、厳格に、着実にコントロールしている。
もっと悲しむべきは、中国本土では多くの人が、ただ暮らしていければそれでよいと考えて、政治がどうであろうと意に介さない。だから、多少でも力を持った反抗勢力というものが形成され得ないのである。
中共は全国の資源を輩断しているので、手当り次第に少しばかりの金をばらまきさえすれば、それまで直訴していた者もすぐに感激の涙を流す。中共が気分にまかせてわずかばかりの福利を施してやりさえすれば、それまで抗議していた者もすぐに言うことを聞くようになる。中共が「ぶっ殺すぞ」と大喝一声しさえすれば、それまで造反していた者もすぐに散り散りばらばらになり、命からがら逃げるようになる。
東欧各国が共産党政権を終結させることができた理由は、それらの国では国民のほとんどすべてが行動を起こし、また軍隊や警察は中立を維持するとともに、場合によっては銃口を反対方向に向けることさえしたからである。ところが中国では、1989年の民主化要求運動でも、また法輪功学習者による集団事件でも、そしてまた香港で起きた真の普通選挙を求める抗争でも、中共を脅かすようなことは何1つなかったのだった。
もう1つ、国外のことを考えても、中共に制裁を加える勇気のある国はいくらもないということが挙げられる。中国は土地が広くて人口も多く、製造大国であると同時に消費大国でもあり、その一挙手一投足が世界経済の全局面に影響を及ぼす国である。
欧米の先進国はこれから先も中国とのビジネスを続ける必要があり、またアジアの発展途上国は今まさに中国と提携して互いの利益を図る必要があり、そし発展が遅れているアフリカの国々は、それ以上に、中国の援助を必要としている。そういうわけで、多くの国は、中共の覇権主義に大きな不満を抱いていても、口先でちょっと非難することしかできない。関係が多少冷え込むことはあっても、そこには実質的な制裁行動がなく、中共政権に影響を与えることができない。
中国は悲しむべき国である。これまで一度たりとも「民心を得た者が天下を取る」ということがなされたためしがなく、邪悪な者・凶悪な者たちに国土を奪われ続けてきた国だからである。
また、民心を失った者が天下を失うというのではなく、正直で温厚な者(たとえば国民党)が天下を失うという国だからである。明朝朱家の歴代の皇帝はみな残虐非道であり(宵宮が一手に権力を握っていた時の残虐非道ぶりはそれに輪をかけたものだった)、多くの人が切歯掘腕していたが、それでも明朝は276年も確固として揺るがなかった。
だから、読者のみなさんは、「中共は民心を失っているからまもなく瓦解するはずだ」などと軽々しく考えてはいけないのである。
(「月刊中国」2015年9月号より)
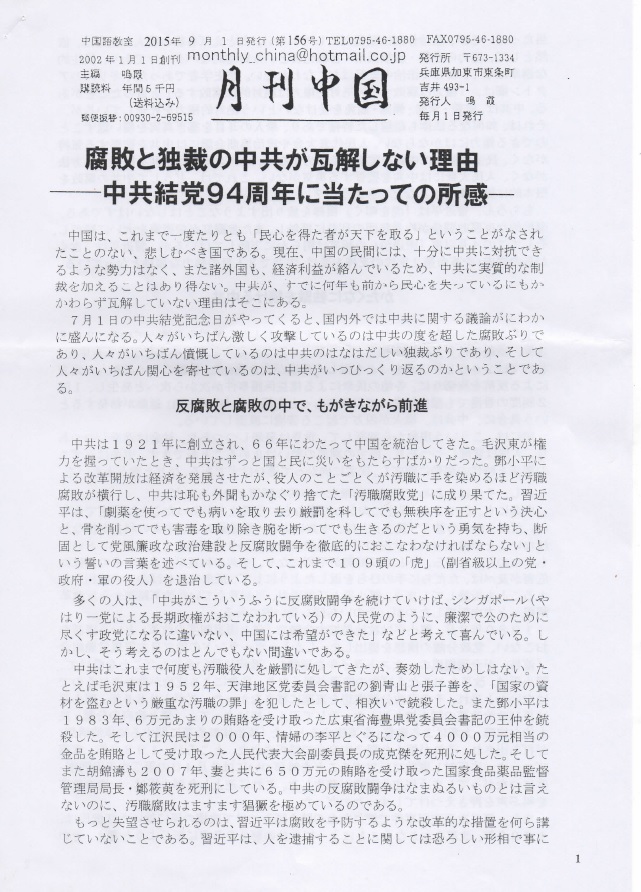 |
◇「月刊中国」定期購読のお申し込み方法 |
 |
◇雑誌「フリー・チャイナ-最新中国事情-」 電子書籍で創刊!鳴霞氏へのインタビューを中心に構成された、新しい情報誌です。Amazonから試し読みも可能。 |